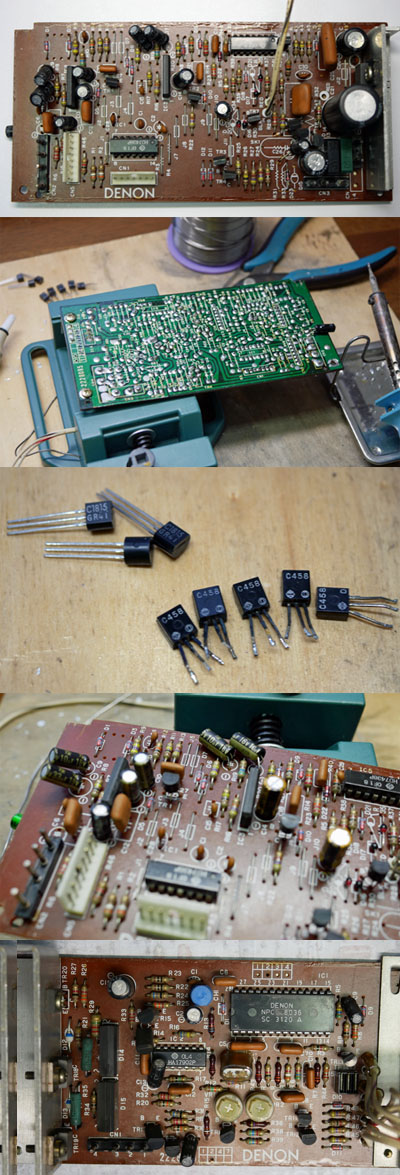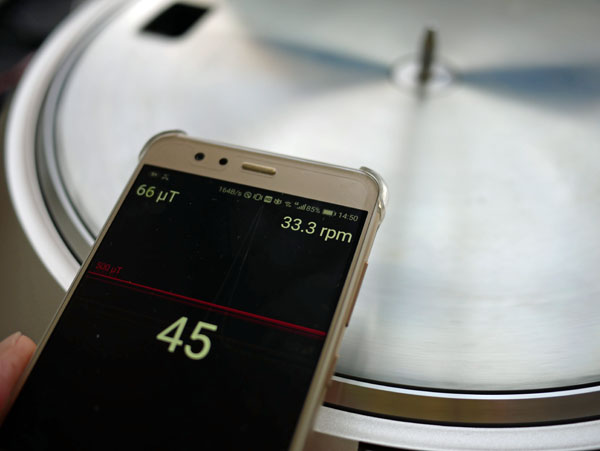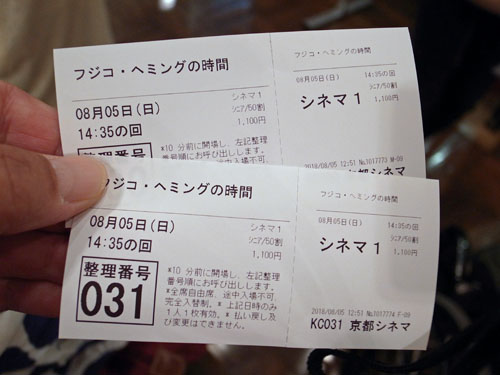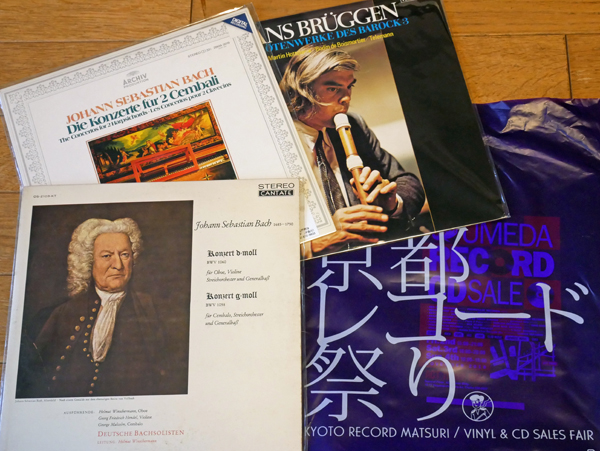ハンブルクに出張した息子がみやげを買ってきてくれました。「ニーダーエッガーをお願い」と奥さまが頼んでました。
ニーダーエッガーは、ハンブルクにも近いハンザ同盟都市のリューベックにあるニーダーエッガーという店が作っている名物のマジパンです。 粉末のアーモンドと砂糖などを練り込んで、チョコレートでコーティングしてあります。ピスタチオ、オレンジ、パイナップル、エスプレッソといろいろ味付けされています。
シットリとしたアーモンド粉の香りとチョコレートの甘さが口に広がります。
15世紀初めにリューベックが飢饉に見舞われたとき、パン職人が倉庫に大量に眠っていたアーモンド使って作ったのが起源とされています。今では、ニーダーエッガーがマジパンの店として知られています。
2010年にリューベックを訪れたときには、ニーダーエッガーの本店で昼飯を食べました。
レシュティというスイスのジャガイモ料理の上に小エビがのってます。
時間がなくて、「早くして! 早くして」とウェイトレスをせきたてて、ヘンな顔をされたことを覚えています。
ハンブルクを離れる朝、ホテル近くのスーパーにニーダーエッガーが並んでいるのを見つけました。奥さまが機内持ち込みバッグにそれらを入れて飛行機に乗ろうとすると、ハチミツの小瓶が手荷物検査で引っ掛かりました。親切な係員が「そこの自動販売機で、ジップケースを2個買って、そこ入れろ。2ユーロだから」と教えてくれました。廃棄は免れて日本へのみやげとなった、思い出の味でした。