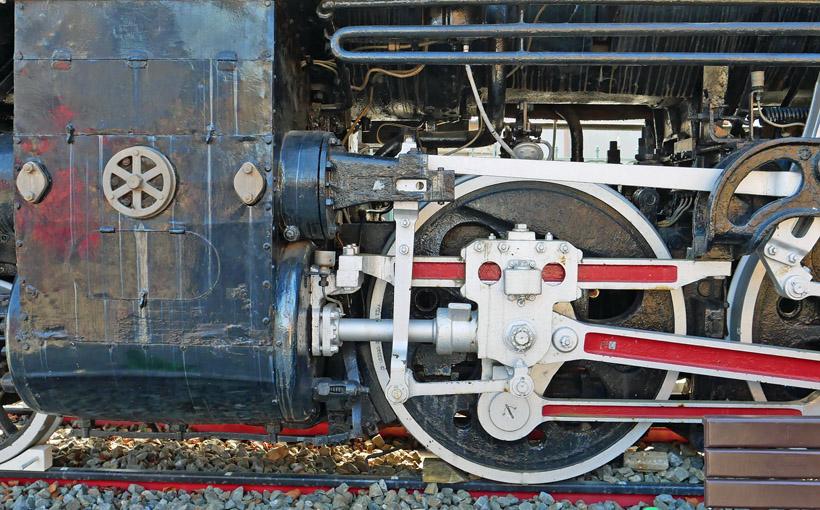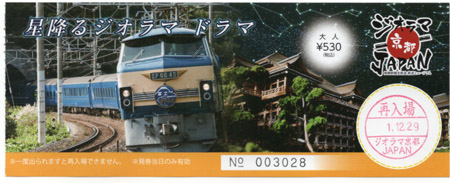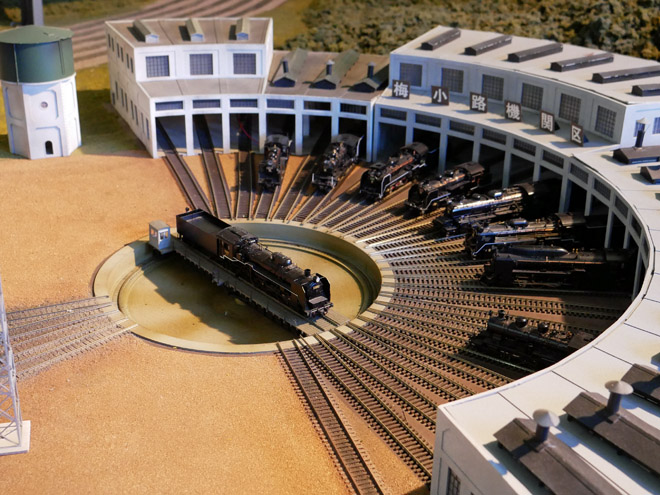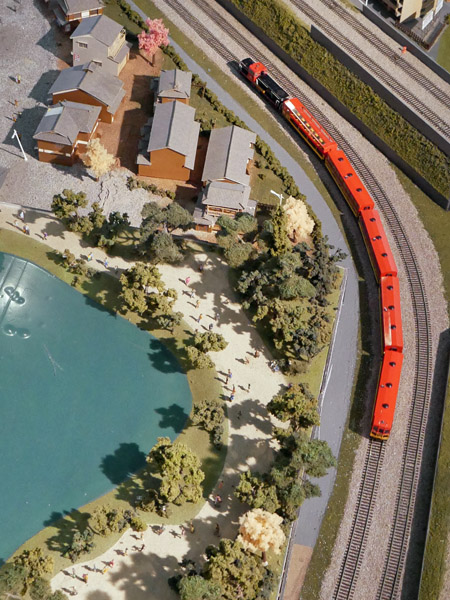兵庫県立美術館で開かれている「ゴッホ展」を見に行きました。
昼飯は、奥さまがテレビで見た「あのオムライスを食べたい」ということで、車を走らせて新開地の「グリル一平新開地本店」でいただきました。
昼営業オーダーストップの寸前に滑り込み、「オムライス」(850円)と「Cセット」(2200円)を頼みました。
エビとホタテ、白身魚のフライにポークチャップの豪華版です。洋食屋のランチにお決まりのロースハムがついているのもご愛敬です。
ポークもフライも、どれも平均点にうまいです。庶民の町の洋食屋さんそのものの、安心して食べられる味でした。
濃厚味のポタージュスープがついています。
こちらが定番のオムライスです。
最近、増えてきたフワフワ玉子ではなく、薄焼きの玉子が覆ってます。
真っ赤なケチャップではなく、デミグラソースがかかっています。
カウンターの上には、知ったタレントの写真と色紙が並んでいます。
店を出たときは、「仕込みのため5時から営業」のお知らせが。
三宮や元町にも店はあります。最初は南京町近くの元町店に行きましたが、近くのコインパーキングは30分300円。これはダメと新開地に転進したら、30分100円でした。
グリル一平 新開地本店
078-575-2073
神戸市兵庫区新開地2-5-5 リオ神戸 2F
今朝の「日曜美術館」(NHK-Eテレ)は、ゴッホ展でした。その説明で見どころを押さえて出かけました。チケット(主催・産経新聞社など)が1枚あったので、わたしはシニア割引を購入しました。半額でした。
コロナも騒いでることだしと、タカをくくって出かけると、予想外の大混雑でした。
ゴッホの作風が、時代とともに変化していくのがよくわかる展示でした。ただ、ゴッホを代表するような自画像やヒマワリといった作品はなく、ちょっとさみしいでした。
アムステルダムのゴッホ美術館は、2回も前を歩いておきながら、入ったことがありません。残念なことをしたものです。