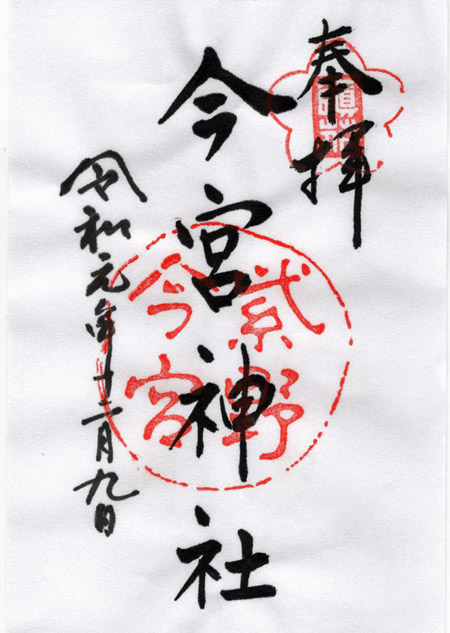久しぶりに京都の町を歩きました。阪急で河原町までやって来たのは、半年ぶりです。
とりたててアテはなく、「京都人の密かな愉しみ」(NHK-BSで2015年から17年まで不定期に5作が放送されたテレビドラマ・ドキュメンタリー番組)のロケ地を鴨川に沿って思いつくままに巡りました。
さて、この気持ちよさそうなベンチは、どんなシーンだったでしょうか?
京都は、盆地の下を豊かな伏流水が北から南へと流れています。ドラマでもあちこちの名水(神水)が紹介されました。
阪急・河原町から歩き始めて、ほとんど観光客がいない朝の新京極を上ります。すぐの右手にあるのが錦天満宮です。この境内の「錦の水」が番組でも紹介されました。ただし老舗和菓子屋の若女将、沢藤三八子(常盤貴子)は登場しません。
「銅駝(どうだ)の水」です。夷川を河原町から東に入った銅駝会館の前にその蛇口はあります。
名水に登録されているわけではない防火用水です。それでもおいしいと汲みに来るファンが絶えないそうです。
番組でも、「珈琲夢譚」のマスターが自転車で水を汲みに来るシーンで登場します。
「染井の水」は日本3名水(醒ヶ井、県井、染井)のひとつです。御所の東に接する梨木神社にあります。
番組では洛志社大学のエドワード・ヒースロー教授(団時朗)が、「この水で割る日本のシングルモルトは最高だ」とうなります。