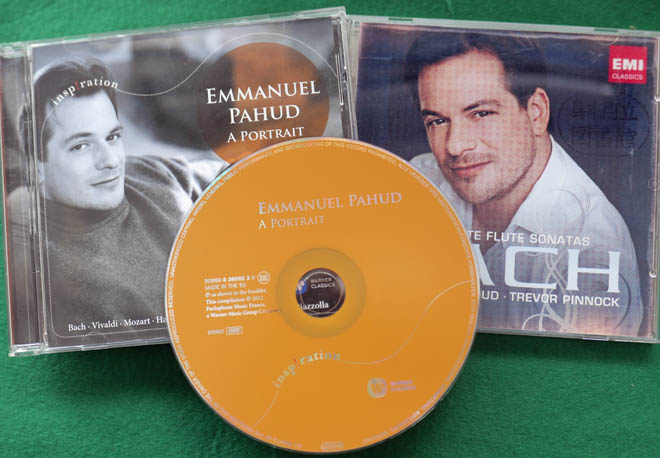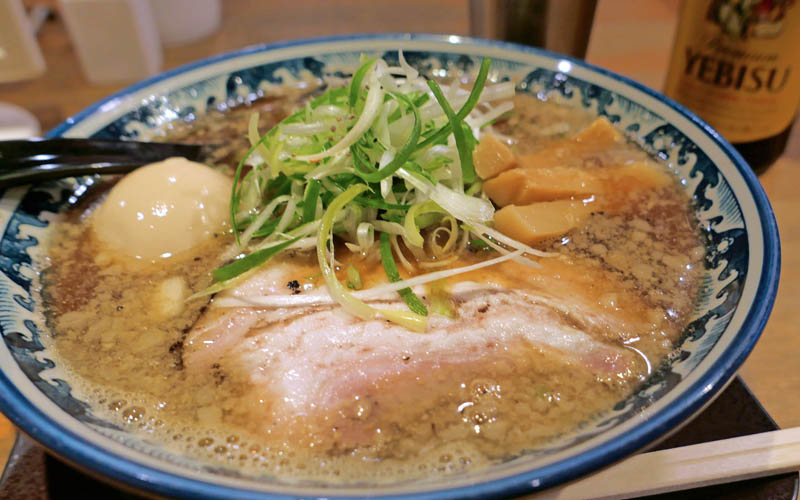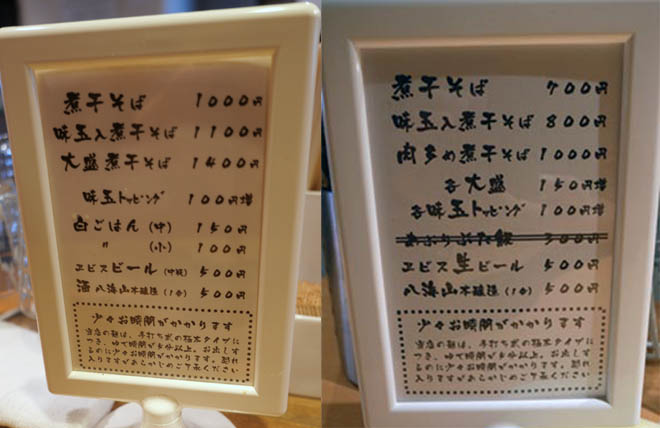京都・岡崎の京都国立近代美術館で「若きポーランド [色彩と魂の詩 1890-1918]」を楽しみました。
オルガ・ボズナンスカの「菊を抱く少女」です。圧倒的な眼力で見つめられました。黒く大きな瞳ばかりを見返してしまいました。吸い込まれてしまいそうな、なんとも不思議な絵でした。
1点を除いてカメラ撮影が許可されていました。わたしもカメラを向けました。髪の毛に室内照明が反射しています。

日本初公開の絵画がほとんどです。その中からポスターにも使用されていました。
美術館の最寄りの地下鉄・東山駅にも掲示されていました。
「日曜美術館」(NHK-TV)でピアニストの反田恭平さんが「ジャル」という単語で説明していました。これを見て、会期末間際に滑り込みました。

反田さんが、初めて訪れたポーランドで見た秋が描かれています。

ショパンの「葬送行進曲」と同じテーマが描かれているそうです。

カメラ撮影がOKなうえに、「線まで下がってください」というだけで作品との距離も近い展示でした。

「夜明けのブランティ公園」です。国土が消えたポーランドの宮殿を朝もやの背後に置いて、夜が明けるの待っています。

どれも繊細なタッチで描かれています。

ウィーンでのとトルコ軍との戦いを描いています。
サブ・タイトルとなっている20世紀前後に、「若きポーランド」と呼ばれた画家たちの作品が並んでいました。その先鞭をつけたヤン・マテイコの代表的作品です。

近代美術館に入ったのはいつ以来でしょうか。思い出せません。

改装されて、すっかりきれいになっています。
この広いロビーで、反田さんのピアノ演奏会も行われました。ショパンの「ラルゴ(神よ ポーランドをお守りください)」も弾いたようです。抽選に落ちましたが、聴きたかったです。

チケットを買おうとして、JAF会員割引の対象であることがわかりました。ありがたい200円引きです。

暑い一日でした。白川の川辺だけは、涼しい風が吹いていました。向こうが美術館です。