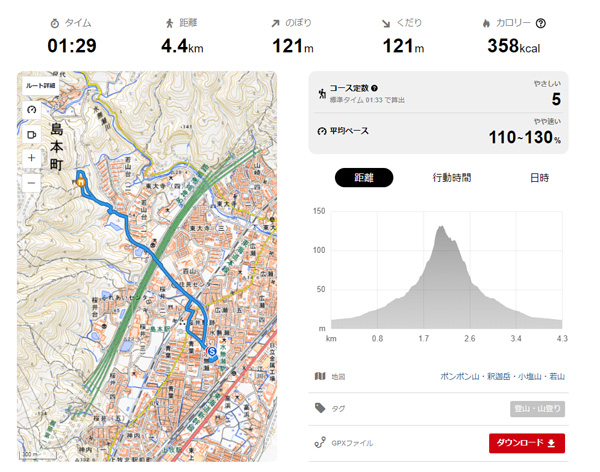京都・西山、大原野神社の幻の桜として知られる「千眼桜」が開花したとの情報でした。満開の期間がたったの3日しかないという、ボタンザクラのような白い花をつける一重の枝垂れ桜です。
慌て者は車でとんでいきました。でも満開にはまだちょっと早かったようです。
手前の小山のような桜です。
大原野神社では、狛犬に代わって狛鹿がお出迎えです。奈良・春日大社の分霊を祀っています
紫式部ゆかりの社としてPRしています。
ことしの京都は、どこに行っても源氏物語です。
椿が大きな花を咲かせています。
真っ赤と赤白まだらの2種が混ざっています。
お行儀よく切り株にポタリ。そんなことはありません。だれかが並べたのでしょう。
落ちた水路では水がしたたります。
雌しべが飛び出しています。雄しべ(?)の格好がちょっと違います。
ミツバツツジも鮮やかです。
大原野神社
075-331-0014
京都市西京区大原野南春日町1152
山手の小径を上って行きます。
「花の寺」として知られる勝持寺です。
西行法師ゆかりの西行桜も咲いています。
紅葉もきれいな寺です。
勝持寺
075-331-0601
京都市西京区大原野南春日町1194