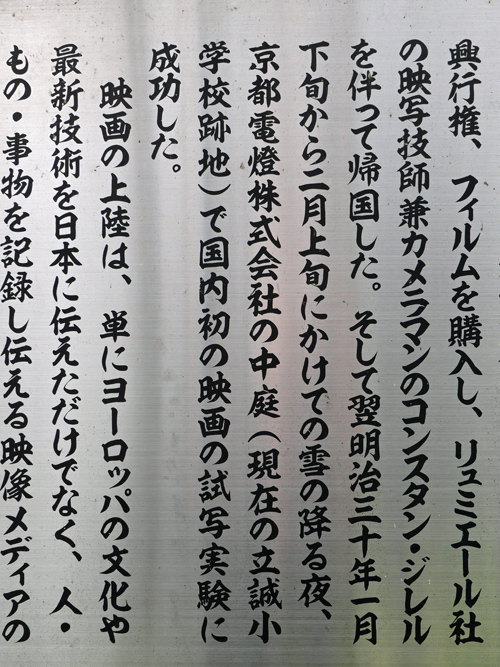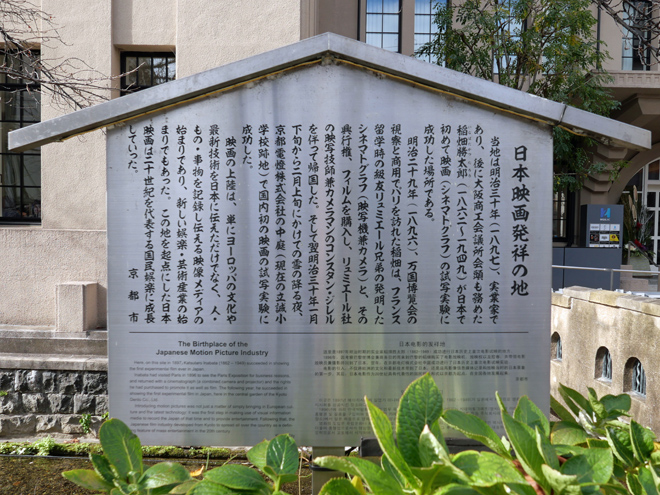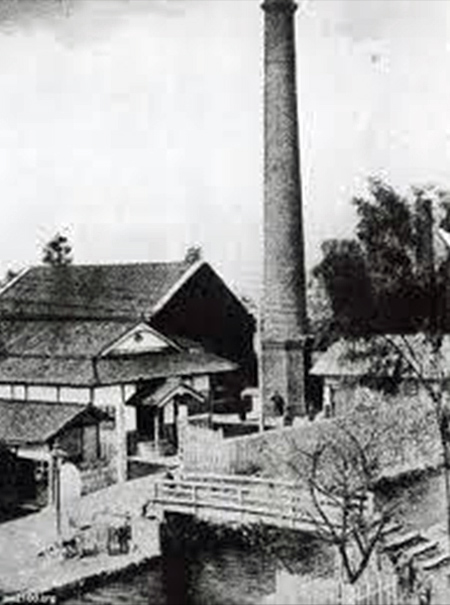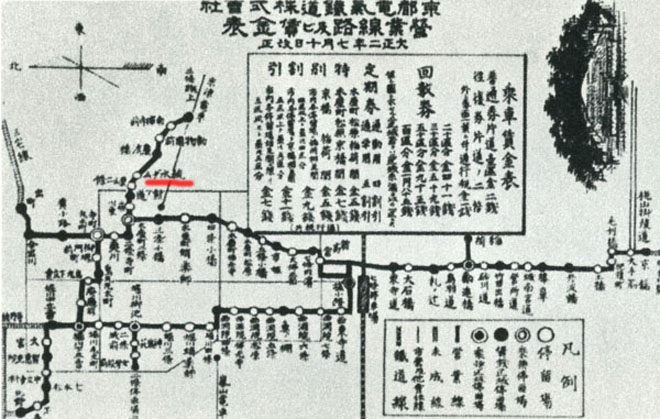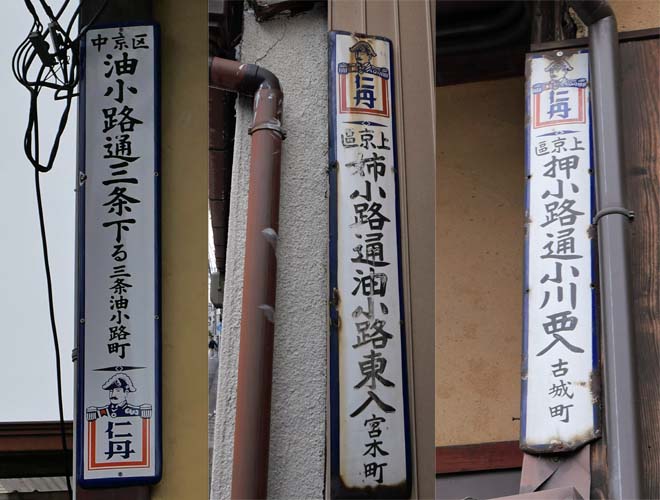久しぶりに山を歩きました。須磨アルプスのこの辺りにはクマは出没しないはずでした。「山と飲み会」のいつもの仲間と一緒です。
まずは山のお茶屋さんを巡るスタンプラリーから、断崖絶壁の馬の背を越え、板宿の居酒屋に飛び込みました。

【2025/11/18 08:55】
山陽・須磨浦公園に集合しました。須磨浦山上遊園は休みで、ロープウェーも休止でした。
天気予報は急激に冷え込むとのことでしたが、太陽も顔を出してこの時点では暖かでした。

仲間2人は体調不良で欠席。4人で歩きました。スマホのGPSアプリ、YAMAPを起動させて出発です。

「ちかみち」を進みます。いきなり急階段の連続で息があがります。

山上遊園の回転展望閣もお休みです。

すぐに最初のピーク、鉢伏山です。

旗振山まで登ってくると、はるか淡路島まで見渡せました。

昭和6年創業の旗振茶屋です。

「神戸にでかけよう スタンプラリー」の台紙をいただき、「旗」のスタンプを押しました。
1番の山上遊園が休日だったのが残念です。

皇帝ダリアンの小型品種でしょうか。薄紫の花をいっぱいにつけていました。

鉄拐山までやってくると、北側の視界が開けました。

4人でポーズです。

おらが茶屋はカレーが名物ですが、食べられるのは土日だけです。

2つ目のスタンプをゲットです。

山際に集合住宅が林立する高倉台に向けて急階段を下ります。向こうが次の目的地の横尾山です。

住宅地を抜けて登りのスタートです。急階を登り返すルートは敬遠しました、

文太郎道を進みます。
「孤高の人」(新田次郎著)で描かれた加藤文太郎は、この道を通って1日で宝塚までを往復したそうです。


ちょっとお腹も空きました。コーヒーブレークとしました。

恒例のおやつ交換会です。わたしは途中の阪急・十三のパン屋でシュトレンを買ってきました。

おいしくいただきました。

次は横尾山です。

三角点タッチです。2等三角点なので指は2本です。そんな流儀があるようです。

コース最大の難所、馬の背までやってきました。

ナイフリッジというほどでもありませんが、切れたった岩場を進みます。

下からも撮られていました。

慎重に進みます。


下を見たら怖いですが、無事に通過しました。


やったー!!とポーズです。

4人で並びましたが、肝心の馬の背は写っていません。

板宿に向けてゆるかかな山道を下りました。板宿八幡神社に淡いピンクのツバキが咲いてました。

お参りしました。

板宿の商店街まで下ってきてゴールとしました。

おいしそうなかまぼこ屋があったので、土産に購入しました。

「炉ばた 一平」に一直線でした。

ちょっと寒かった日にも「おつかれ~生」で乾杯です。

お造りの盛り合わせです。どれもおいしかった。

あれこれといただき、いっぱい飲みました。一杯ではありません。

店主の一平さんも気さくなかたで、気持ちよく飲み進みました。
炉ばた 一平
078-732-0280
神戸市須磨区飛松町3-1-3

スタンプラリーは来年2月までです。もう少し挑戦したです。