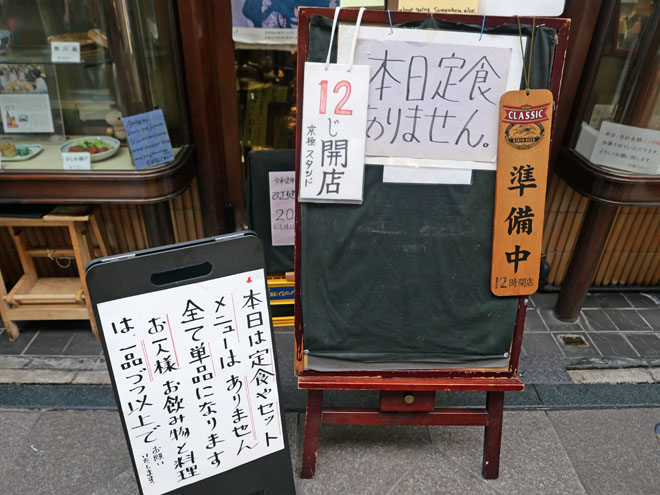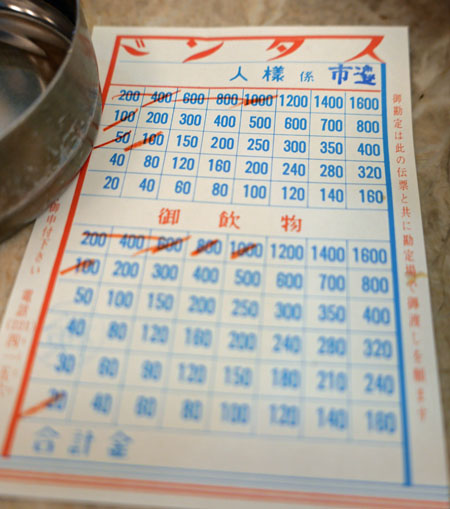おいしいワインをいただきました。「ヒイカのファルシ」とともに最高においしく飲みました。
魚が比較的に新鮮でリーズナブルな近くのスーパーへ行きました。タイが一匹で300円台なんて、信じられない値札で並んでました。スルメイカも新鮮そうでしたが、その横に並んでいたヒイカを選びました。
ファルシはフランス語で肉や魚、野菜などの中に別の食材を詰めた料理だそうです。ヒイカのゲソにイタリアンパセリなんかが詰め込まれています。奥さま手です。
トマトソースはわたしが作りました。生食ではあまり美味しくなかったトマトが、ソースにすると味変しました。
スキレットに並べて、オーブンで焼きました。
パンにつけてもおいしいソースでした。
ドイツ産のリースリングです。キリリと冷やしていただきました。さわやかに、まろやかに、いくらでも飲んでしまいました。ありがとうございます。
刺し身のタイはカルパッチョにしていただきました。
特別な日でもありませんが、ワイン1本で大満足な夕飯となりました。