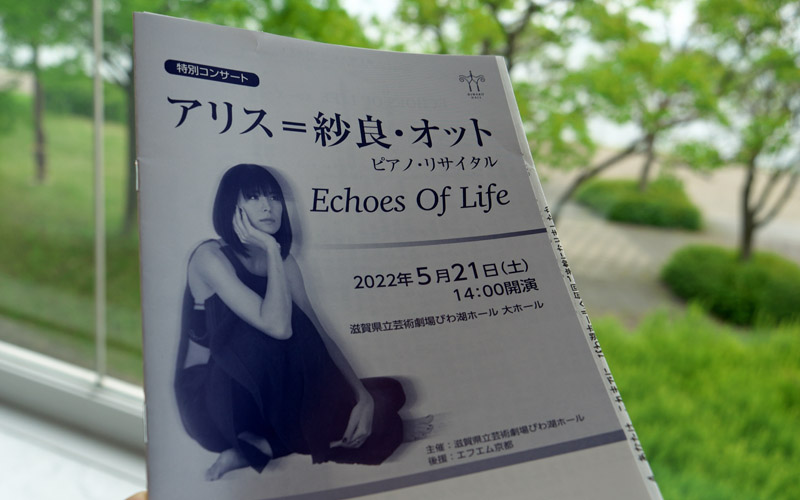わが家から歩いて3分とかからない水無瀬駅前商店街にできた包子(パオズ)と日本茶の「岡村商店」です。早くも開店から1年ほどたちますが、電話予約して初めて訪れました。
自慢の包子3個セレクトとスープ、お茶請け、日本茶の「包子みっつセット¥(1200円)です。
まずは定番の豚まんから。京丹波高原豚のミンチを使っています。ジュワーッと脂がこぼれます。小麦粉を蒸した発酵済みの生地に包まれています。もっちりとしています。熱々です。

キャベツまんは、野菜具だくさんです。調味料や香辛料は使っていないのか、ストレートに野菜の味です。

青菜まんは小松菜がメーンです。
3つもいただくと、さすがにお腹いっぱいです。

新タマネギとワカメのスープも、素材そのもののうす味です。

皮付きのカシューナッツはしっとりとした味わいでした。

日本茶も自慢です。
1杯づつ急須で丁寧に入れてくれます。

食後に2杯目をいれてもらいました。1杯目は上品な甘さが感じられ、2杯目は渋みが深くなっています。

きょう入れてくれたのは「日野荒茶」でした。滋賀・日野町の産です。
いろんな茶葉を販売しています。

カウンターのマスターと話していて、意外な事実が判明しました。
マスターは地元・島本の出身。なんとわたしの息子と高校の同級生でした。「電話予約で名前をうかがったときに、あれって思ってたんです」。すぐ近くでは、同じ幼馴染がバルを開いていています。そんなこんなで話が広がりました。

岡村商店
075-204-9688
大阪府三島郡島本町水無瀬2-3-9