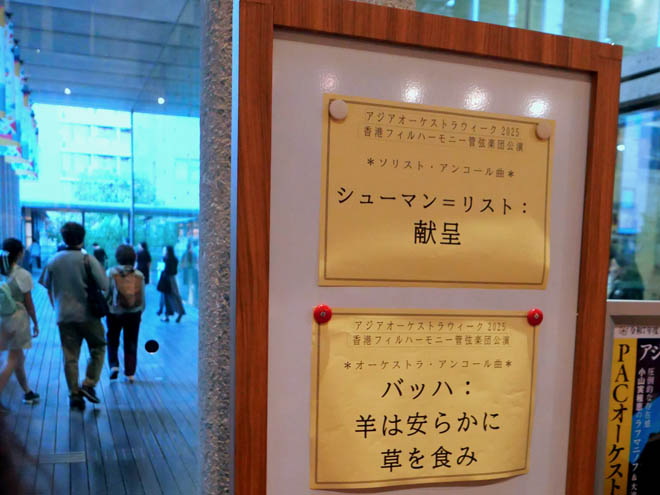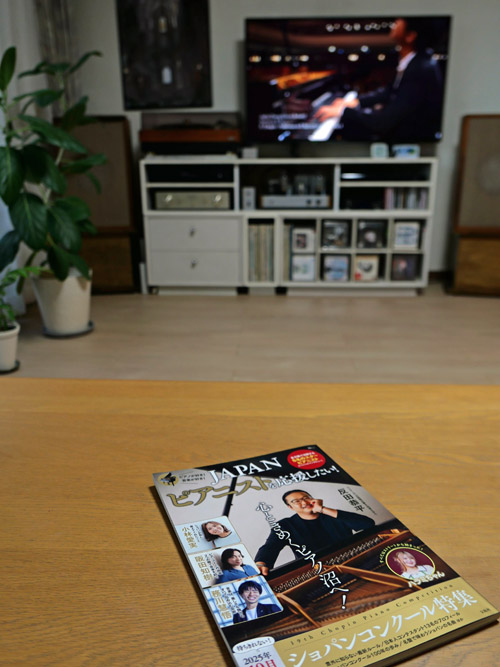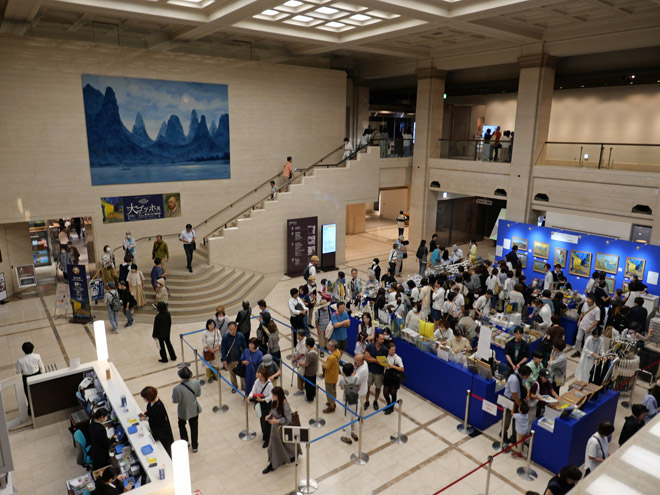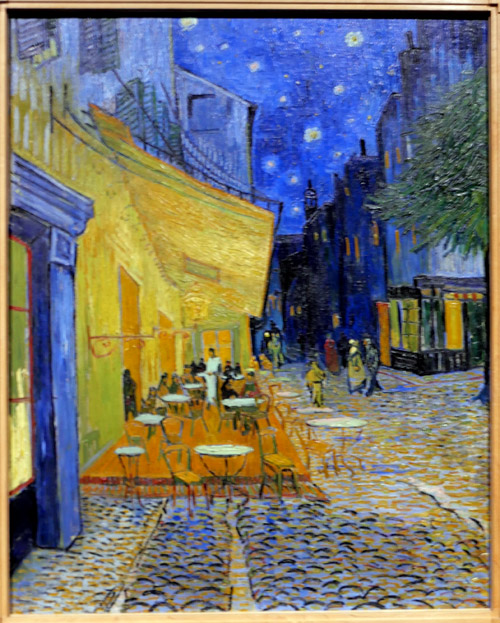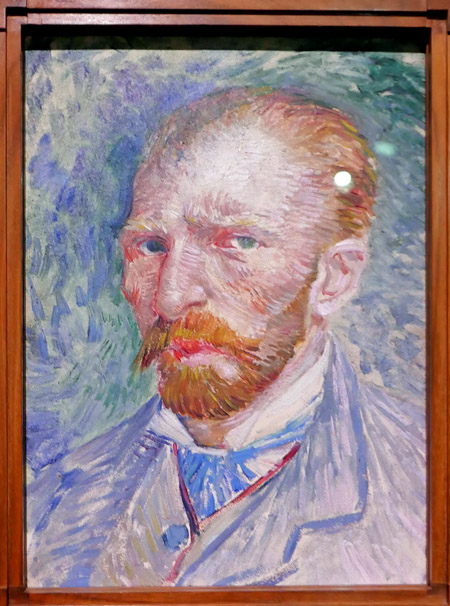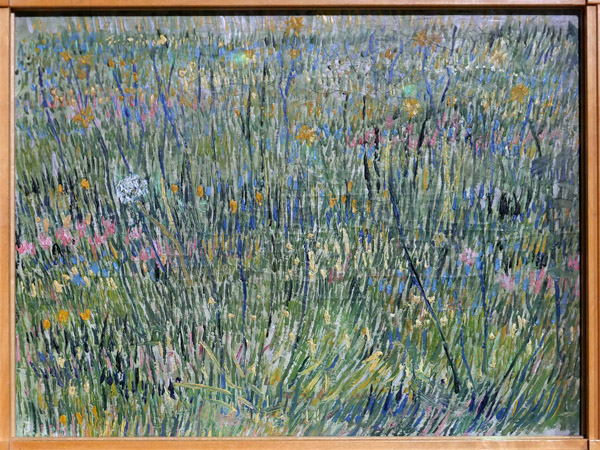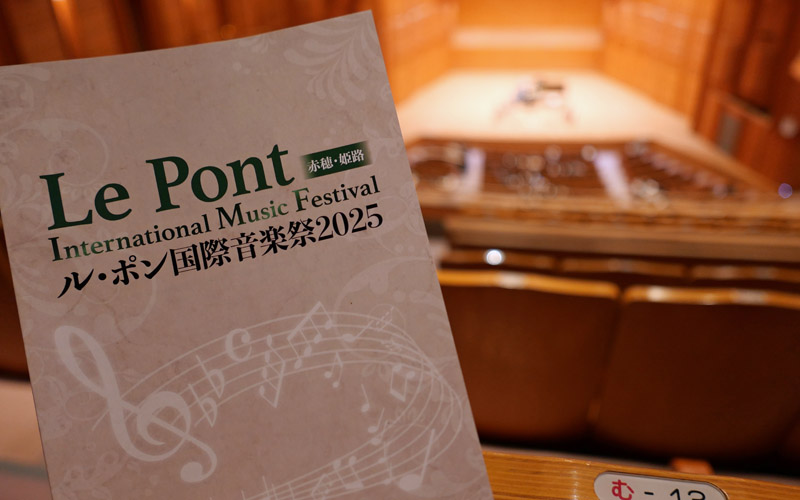「ル・ポン国際音楽祭2025」を、播州赤穂の赤穂化成ハーモニーホールで聴きました(9月30日)。
ベルリン・フィルハーモニーのコンサート・マスターを勤めるヴァイオリニストの樫本大進が音楽監督をつとめ、縁がある赤穂や姫路で6回ものコンサートが行われます。
この夜のプログラムには、樫本はもとよりベルリン・フィルの首席フルーティスト、エマニュエル・パユらも登場。モーツァルトとショスタコーヴィチらの作品が並びました。
チケット発売日の翌日に思い出して、ネット予約しました。ラッキーなことに席は確保しましたが、2階最後尾列の前というステージを見下ろすような席でした。それでもホールの響きは素晴らしく、たった1000円(消費税込み)の席に、その何倍もの高速料金を払ってはるばると車でやってきた値打ちがありました。

圧巻はパユのフルートでした。モーツァルトのフルート四重奏曲第4番では、びっくりさせれるほどの柔らかさで聴くものを包み込む音色を紡ぎました。ショスタコーヴィチの4つのワルツでは軽やかに舞うように、パユもステージでダンスのステップを踏んでいるよう。ベルリンでも聴いたオケの一員としての顔とは別人でした。
樫本は前半の知らない作曲家の2曲に登場しましたが、支える演奏に徹しているようでした。

ル・ポン音楽祭は8年前に聴いています。地の利はそれほどありませんが、満員でした。

早く着いたので、赤穂御崎まで行ってみました。瀬戸内海に向かって伊和都比売(いわつひめ)神社の鳥居が立っていました。向こうは小豆島です。

ミニ・モン・サン・ミッシェルです。岩礁に波が打ち寄せていました。干潮時には渡れるようになるのでしょうか?

きらきら坂と名付けられてショップが並んでいました。

階段にはおしゃれなカラータイルが張られています。

赤穂といえばなんでも四十七士です。いや四十七味です。

ブイが化けていました。

お目当てのガラスショップは臨時休業でした。
この後、夕食に穴子丼を食べるつもりだった店も開いておらず、あての「ハズレ」ばかりが連なりました。