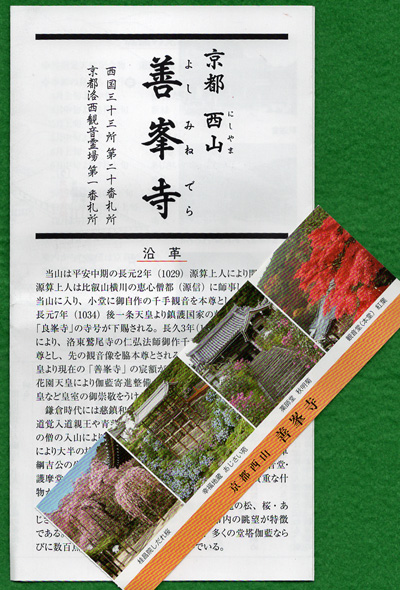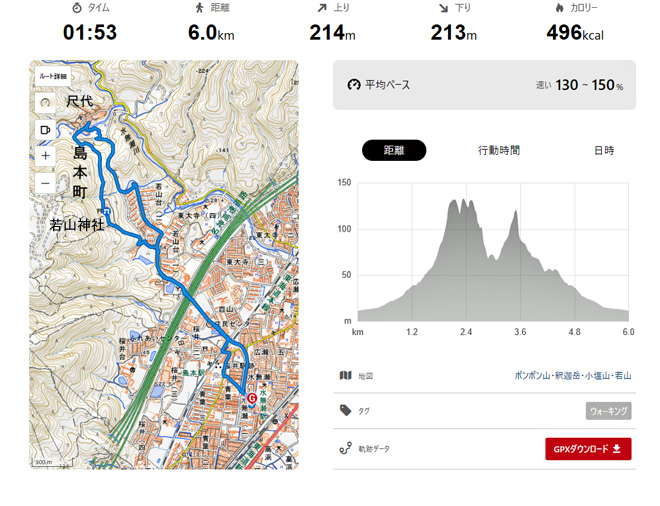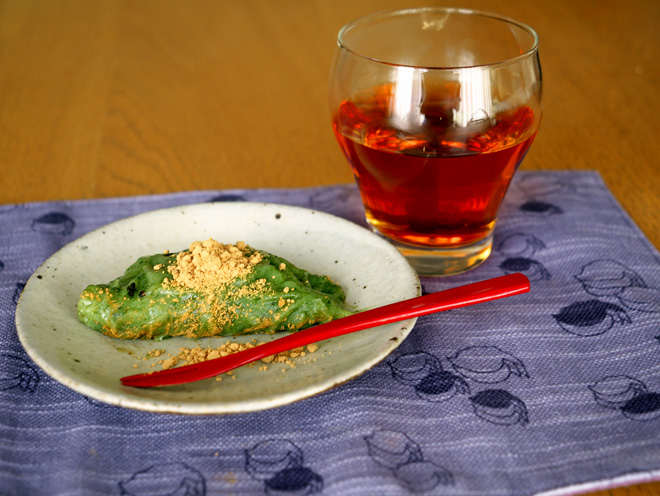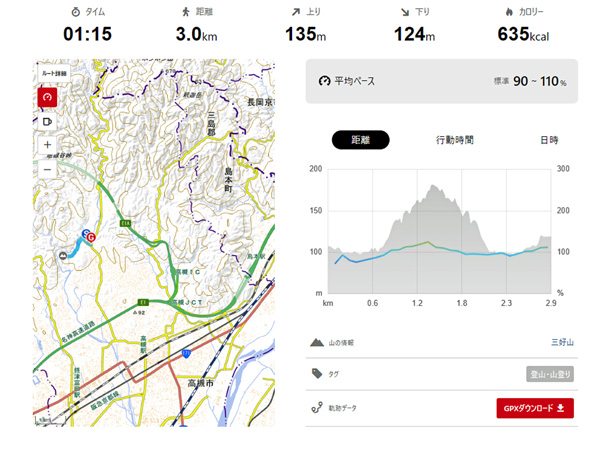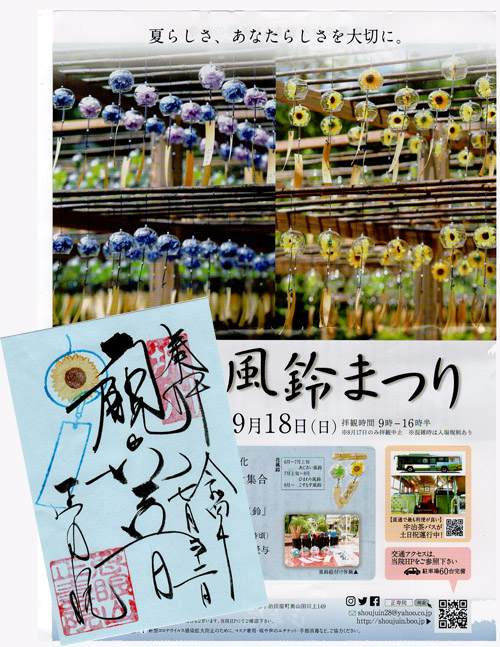京都西山の西国札所、善峯寺に参りました。山の中腹(標高約300m)にあり、秋の訪れもひと足早いです、
シュウメイギク(秋明菊)が、満開を迎えていました。ピンクに白と競っています。
濃いピンクの八重咲です。キク(菊)とよく似てますが、アネモネの仲間です。
どこかわびしげな表情もしています。
建立は平安中期の古い寺です。
ポンポン山の東の登山口としてもよくやって来ます。きょうはカメラをザックに、クルマでした。
ムラサキシキブ(紫式部)が、紫の実を垂れています。
徳川五代将軍、綱吉の生母、桂昌院を大檀家としていました。
桂昌院建立の経堂に、桂昌院お手植えの桜が枝垂れます。
紅葉はもうすぐです。
きょうは、ほとんど参拝者がありません。間もなく西国巡礼のツアーバスもやってきて、にぎわいます。
早くも色づいた葉もありました。
京都市街の向こうに、比叡山から東山三十六峰が見渡せました。
善峯寺
075-331-0020
京都市西京区大原野小塩町1372