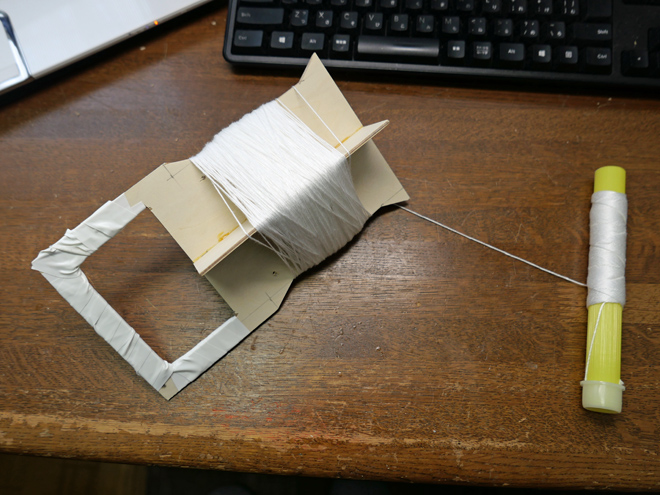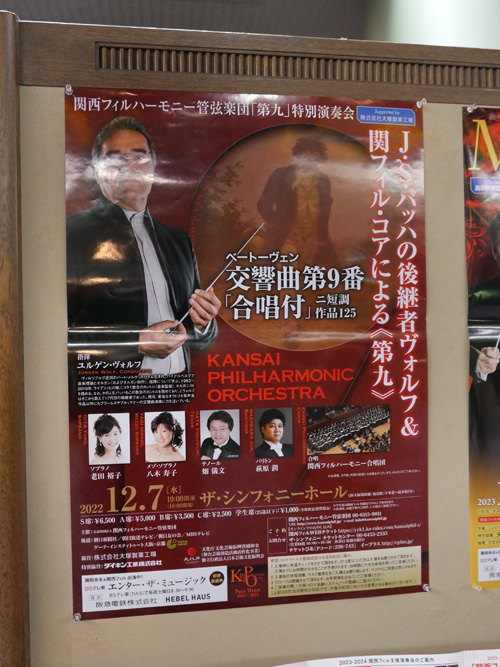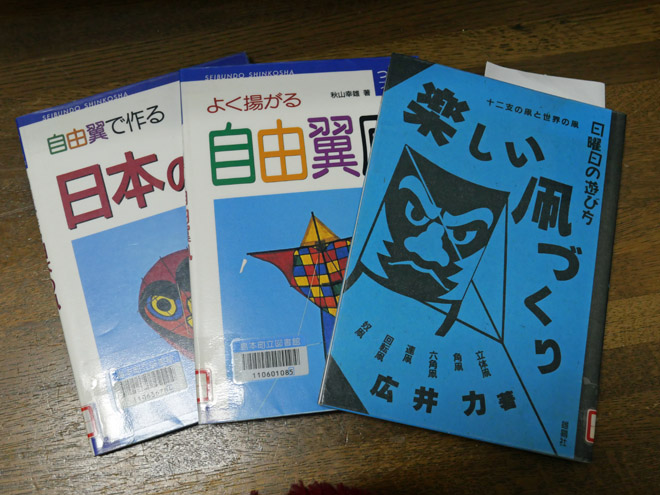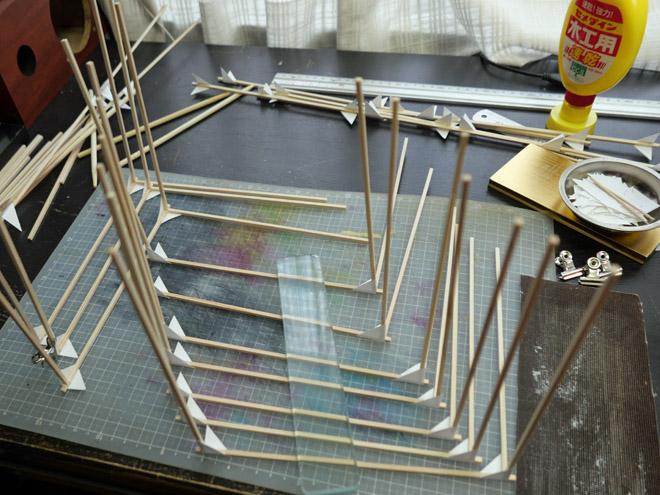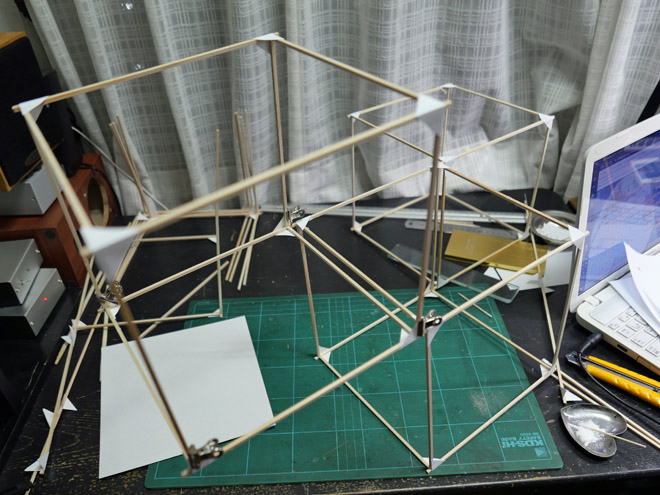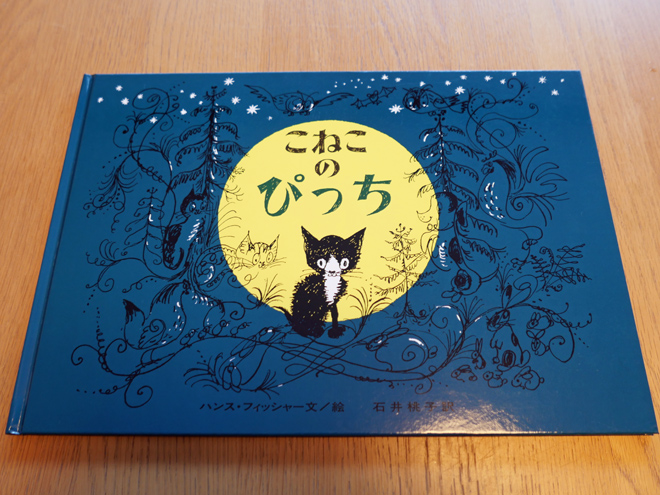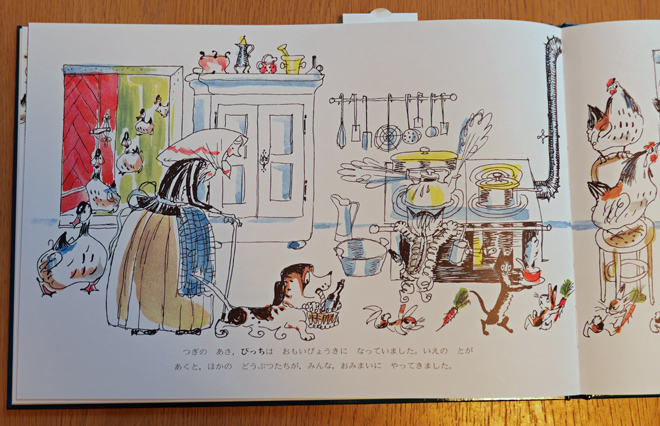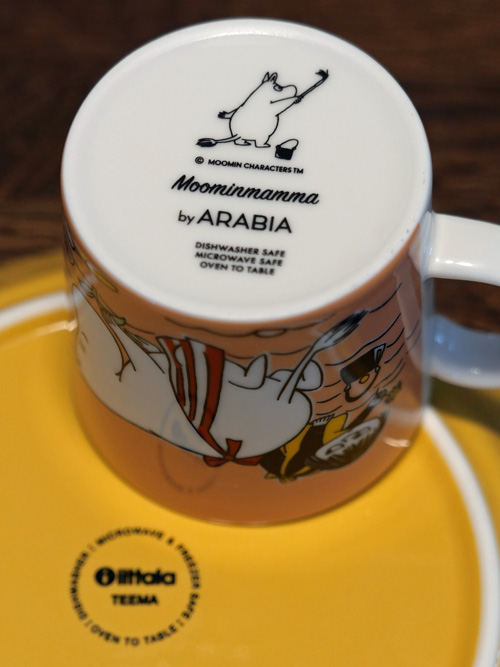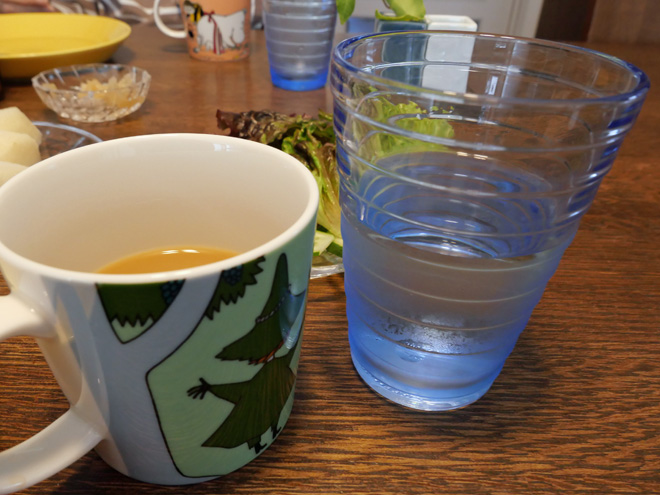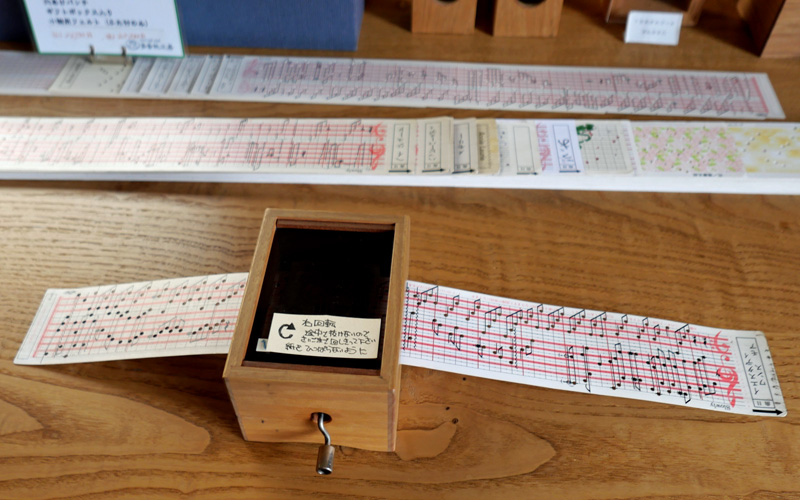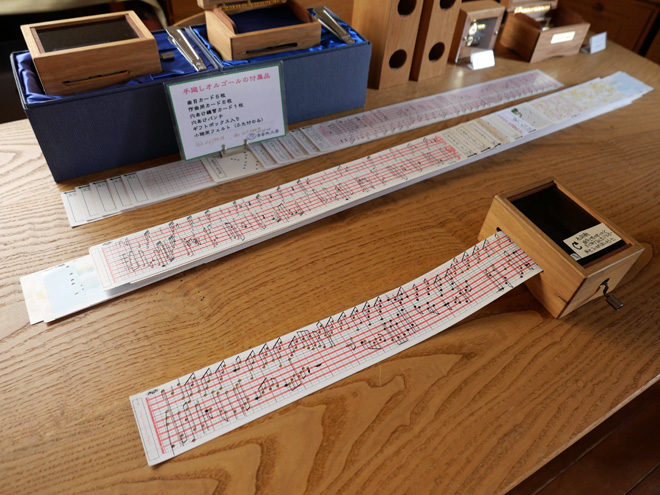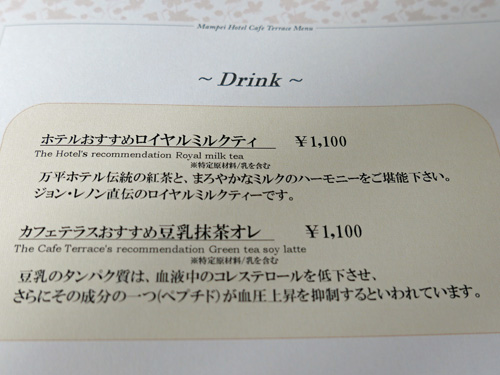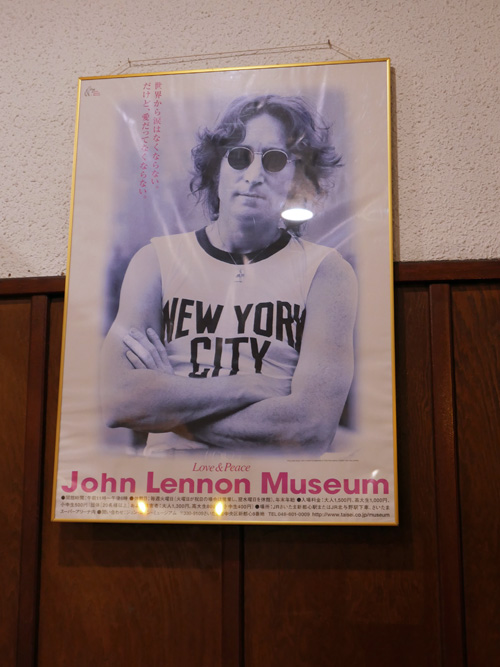宝塚ベガホールでユルゲン・ヴォルフのオルガンコンサートを聴きました。先日、ベートーベンの「第9」を指揮したユルゲンが、今夜はオルガニストでした。独ライプツィッヒの聖ニコライ教会の前カントル(音楽監督)です。
あまり聞く機会がないオルガンの生の音を浴びました。やはり迫力がありました。畑儀文のテノールも、よく響いていました。
最後の1曲には、大阪バッハ合唱団のメンバーが加わりました。バッハの「イエスは変わらざるわが喜び」BWV147とプログラムには書かれていましたが、演奏が始まると「主よ、人の望みの喜びよ」として知っているコラールでした。奥さまも歌ってましたが、リハーサルなしの本番だったそうです。
スイス製のパイプオルガンです。腹に響くような重低音は聴けませんでしたが、鳥がさえずるような弱音の高音は、天国の調べでした。
阪神大震災で大きな被害を受けましたが、きれいに修復されています。
演奏された1曲は、ディートリッヒ・ブクステフーデの作曲でした。聞いた名前でした。
12年前に訪れた独リューベックの聖マリエン教会にかかっていた石版画です。「バッハはブクステフーデのオルガンを聴くために数百キロの道を歩いてやって来た」という説明を思いだしました。
右がバッハです。「Dietrich Buxtehude」の文字も読めます。
宝塚ベガホールの玄関には、ウィーンの市立公園と同じヨハンシュトラウスの像が立っています。