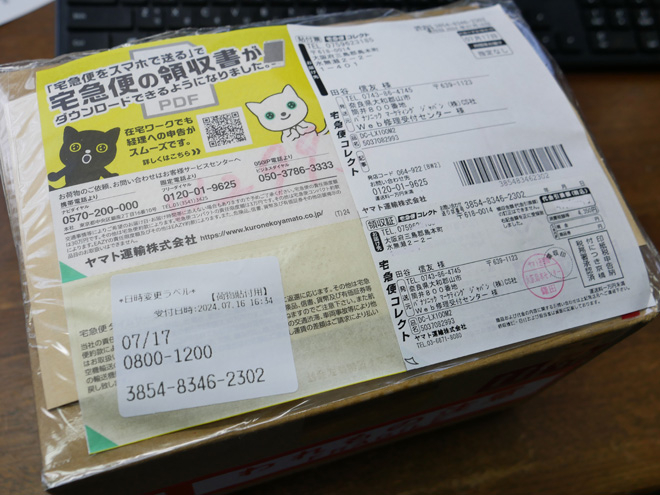各地に風雨の被害をもたらした大きな台風も、幸いにもわが家の辺りではさして影響はありませんでした。いつになくきれいな夕空となりました。
水無瀬神宮の夏の風物詩「招福の風」も、あすが最終日です。ライトアップを撮影してきました。
予想通り、小さな水たまりに光きらめいていました。
カメラの撮影モードを「イルミネーションをキラキラ撮る」にしてみました。光芒が四方に広がりました。
「竹取物語」と名づけられた通路沿いのアートです。
シャボン玉が噴きあがります。
水無瀬神宮
大阪府三島郡島本町広瀬3-10-24
075-961-0078