帰宅途中のJR大阪駅。ジェイアール大阪三越伊勢丹の地階食料品売り場をブラリとしました。
「正月までの今が旬だよ」というかけ声につられて手を伸ばした三重県産の赤ナマコです。すでに調理してあります。
おろし大根を添えて、唐辛子、ポン酢でいただきました。
特段、味が素晴らしいわけでもありません。でもこのコリコリとした噛み心地は、ナマコです。好物です。
お相手は、焼酎の湯割りです。残念ながら燗酒は苦手です。
ジェイアール大阪三越伊勢丹は、阪神や阪急ほど込んでなくて、散歩には最適です。
再び、おおかたの方には、何のことかという書き込みです。
ジャンクボックスにTELEFUNKENの「ECC802S」という真空管が1本眠ってました。ユーナナ(12AU7)の高品質管です。愛用している2A3ppのメーンアンプの初段管に使われています。試しに差し替えみました。
モーツァルトのヴァイオリン・ソナタのCDを聴きました。素晴らしい。アンネ・ゾフィー・ムターのヴァイオリンが艶々としています。テストを忘れて最後まで聴いてしまいました。
わが家の信頼できる音質測定器さま(奥さんの耳)も、「このピアノの方がホンモノ」と。
テレフンケンのダイヤマークは、はっきりと刻印されてます。
12AU7のバリエーションです。
左から、東芝の「12AU7A」です。最後に「A」がつくのはローノイズ管です。新品で1本800円でした。
米軍仕様の「JG5963」も仲間です。GE(General Electric)のロゴがついてます。
EH(Electro-Harmonix)は、比較的新しいロシア製です。これまでは、これで聴いてました。
右端が、大トリで登場のTELEFUNKENの「ECC802S」です。一度聴いてしまうと、これで決まりです。
おおかたの方には、何のことかという書き込みです。ご勘弁を。
FACEBOOKのお友達の書き込みにつられて、わたしも。
ECC83(12AX7)という真空管です。日本を含めて多くのメーカーで製造されました。
これはドイツのTELEFUNKEN(テレフンケン)製です。音が良いということで、いまや「お宝」となっている貴重品です。
その昔、といっても1980年代あたりまでは、ちょっと奮発すれば買える程度の珍しくもない真空管でした。わたしも1本1500円(記憶はあいまいです)だったかで購入した記憶があります。
これは、オーディオ・メーカーに勤めていた兄に譲ってもらったものです。わたしと違って几帳面な性格で、購入日と思われる昭和42年の日付けがあります。
9本のピンの間には、ホンモノの証明の「ダイヤマーク」があります。
LPレコードを聴くためのフォノEQ(イコライザー)アンプの初段に差してみると、他とは一皮むけた素晴らしい音がします。
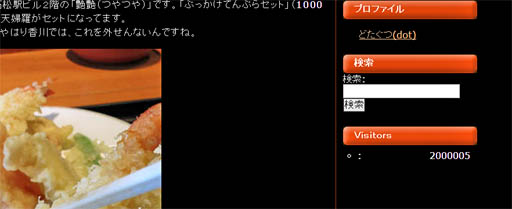
このブログへのアクセスが、200万回を突破しました。いつも、いつもご愛読ありがとうございます。
100万回を突破したのは2011年4月でした。ちょうど四国のお遍路を始めたころです。それから2年半。お遍路の方も間もなく「結願」できそうです。これからも、「食べる」だけでなくいろんなことにチャレンジして、このブログを書き連ねていきます。
このブログの歴史はコチラ
83番札所・一宮寺までは、ことでん(高松琴平電気鉄道)に乗りました。JR高松駅から高松築港駅にやってくると、ホームの電車が発車直前でした。自動券売機で乗車券を買っていては乗り遅れそうでしたが、「車内で乗車券を買ってください」と改札はフリーパスにしてもらい飛び乗りました。
何も知らずに飛び乗った電車ですが、あちこちに一眼レフを抱えた「撮り鉄」がいます。へエー、人気なんだと。
木造にニス塗りの円柱には、ギリシャ建築のような彫刻が施されています。
車内で発行してもらった乗車券もレトロです。「10」と「7」をパンチして17日です。ナンバーは「023」となってます。偶然でしょうか。それとも車両番号でしょうか。降車の際に渡しましたが、記念にもらっておくのだった。
運転席もシンプルです。ガタゴトと揺れながら走ります。
一宮駅に着きました。
「ホームに降りて撮影してください。ご要望があれば申しでてください」とものすごいサービスです。乗客がパンフレットをもらっていたので、「わたしもいただけますか」。それで人気の秘密がわかりました。
「20型23号車」は、元々は大阪鉄道(後の近畿日本鉄道)の車両で、1925年(大正14年)に川崎造船所で製造されました。譲渡を受けた後も今に至るまで現役で走っている日本最古の車両だったのです。
2両連結してますが、貫通はしてません。
先頭のこちらの方がレトロに見えた「3000型300号」は、ことでんオリジナル車両で、「近代化産業遺産」の認定を受けてます。でも製造は1926年(大正15年)と、26号の1年後です。
1日に1往復しかしていない「レトロ電車特別運行」に運よく巡りあわせていたのです。
ガイドブックを見ていると、古い橋梁などとともに屋島駅も近代化産業遺産に認定されてました。
84番札所・屋島寺を打った後、雨に降られて高松に戻る途中でここから乗車しました。

南丹市日吉町の道の駅「スプリングスひよし」に立ち寄りました。日吉ダムの直下にある、大きな施設です。日帰り温泉もあるので「スプリングス」です。
野菜売り場をのぞくと、ありました。「黒豆枝豆」です。10月中旬の2週間ほどの今が旬です。採ったばかりの枝付きも並んでましたが、いずれ新鮮だろうと切り離した袋入りを買い物かごに入れました。
夕食に、ワインとともにいただきました。ねっとりとした濃厚な味わいです。夏の大豆の枝豆のさっぱり感とは違って、やはり秋の味です。
おいしい手造りソーセージも並んでました。同じ南丹市美山町の「美山おもしろ農民倶楽部」の産です。2週間前にも食べたばかりですが、あのプリプリの味が忘れられませんでした。
マスタードをたっぷりとつけて、端からかぶりつきます。
今回は「ハーブ」です。長さがバラバラなのが手造りらしくてご愛嬌です。
色がきれいでゲットしたパプリカもなすとともに食卓に上りました。
トマトは、昨日の残りの生ハムでくるみました。ベランダのバジルも、そろそろおしまいです。
これもワインによくあいます。
スプリングスひよし
京都府南丹市日吉町中宮ノ向8番地
0771-72-1526
美山おもしろ農民倶楽部
京都府南丹市美山町内久保池ノ谷33
0771-77-0890
淀川対岸の楠葉にある、こだわりの紅茶専門店です。この夏、東京・表参道にも進出したそうです。
いい音を出すようになった愛車でバッハを聞きながらちょっとドライブしました。奥さんの友達のお嬢さん夫婦が開いておられる店です。
大阪・堂島の紅茶専門店「ムジカ」は閉店ましたが、ティー好きが減ったわけではないようです。
メニューの説明を聞いていると、あれこれ試してみたくなります。そんな気持ちを察したのか、「ポットでお出ししているんですが、カップで3種類お飲みになられますか」とうれしいご提案でした。
最初は、ダージリンの春摘みです。茶園の農場名までは覚えきれませんでした。
薄い色をしています。いわゆる紅茶色とは違います。飲んでみても、日本の緑茶に近い感じですが、香りが素晴らしいです。
器は、すべてハンガリーのヘレンド窯だそうです。それにしてはちょっと変わったデザインですが、「直輸入したものです」。
こちらは、典型的なヘレンド窯です。
次は、同じダージリンですが夏摘みです。ちょっと味わいが深くなってます。
最後はアッサムです。もっとも紅茶らしい(?)味わいです。砂糖をちょっと入れてみました。紅茶の渋みが緩和されるのか、飲みやすくなりました。この砂糖壺はマイセンだそうです。
白い壁に北欧家具なども配した落ち着いた空間です。
輸入された茶箱が積み上げられています。
テイクアウトできるフレーバーティーなどが並んでいます。
I TeA HOUSE(アイティーハウス)
072-856-3255
枚方市南楠葉1-6-8 プレザントハウス102
カーオーディオのドア・スピーカーを交換しました。ところが、ダッシュボード上に埋め込まれているツィーターは手つかずでした。高音域を担当するスピーカーです。中低音域部だけの交換では、やはり音のバランスが崩れてしまいました。購入したスピーカー・セット、「FOCAL ISS165」には、ツィーターも付いています。これは交換しかありません。
というわけで、3連休の3日目も作業となりました。といっても取り換え工事はドア・スピーカーとは比べ物にならないくらい簡単で、午前中に終わってしまいました。
さっそくグレン・グールドのCDを聞きました。ピアノの音が、車内に広がりました。バッハのカンタータ、モーツァルトの室内楽と、とっかえ、ひっかえ聞き比べて、思わず頬が緩みました。それなりのカネと時間を費やしたかいがありました。
以下は今回も、わたし自身の備忘録です。
新しい愛車となったシトロエンC4の不満は、カーオーディオでした。折角のCDが、シャリシャリした昔のラジオのような音でしか鳴りません。ちょっとがっかりとしていました。でも、同じ思いをしている人はいるようす。DIYで、スピーカーを取り換えているブログがありました。ならば~。
秋晴れとなった日曜日ですが、わたしにとっては「日曜大工」の日となりました。以下のページは、作業の過程を追った、私自身のための備忘録です。
なんだかつぎはぎだらけのようなドアですが、笑わないでください。意味があるんです。