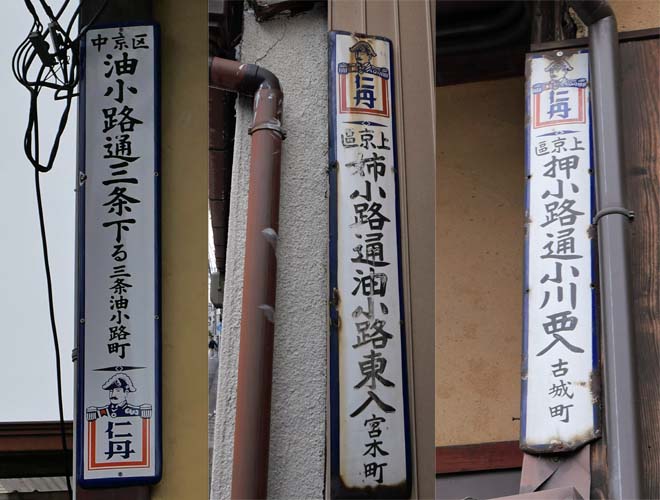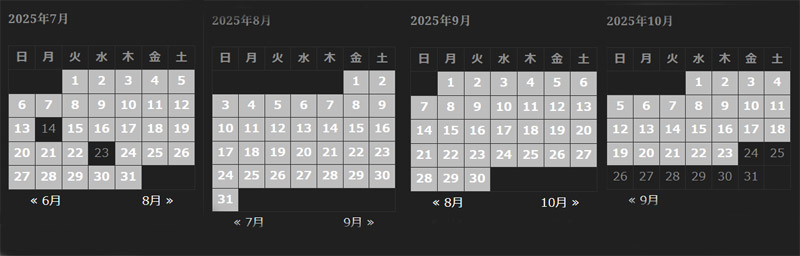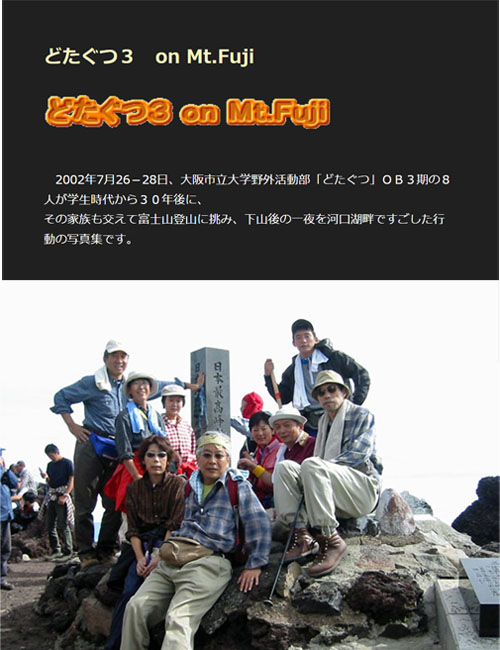Top of Europe、ヨーロッパで一番高所にある鉄道駅、ユングフラウヨッホにやってきました。アルプスの山々や、眼下に流れ落ちるグレッチャー氷河が見渡せるはずでした。
期待に反して生憎の空模様。眼の前にそびえるスフィンクス展望台ですら雪に霞んでいました。

ただただ寒さに震え、足跡を記しただけでした。
クライネシャイデックから乗り継いだユングフラウ・バーンは、アイガーの山腹をぶち抜いた景色のないトンネルをひたすら登りました。
クライネシャイデックに戻ってきての昼飯は、目玉焼きでした。